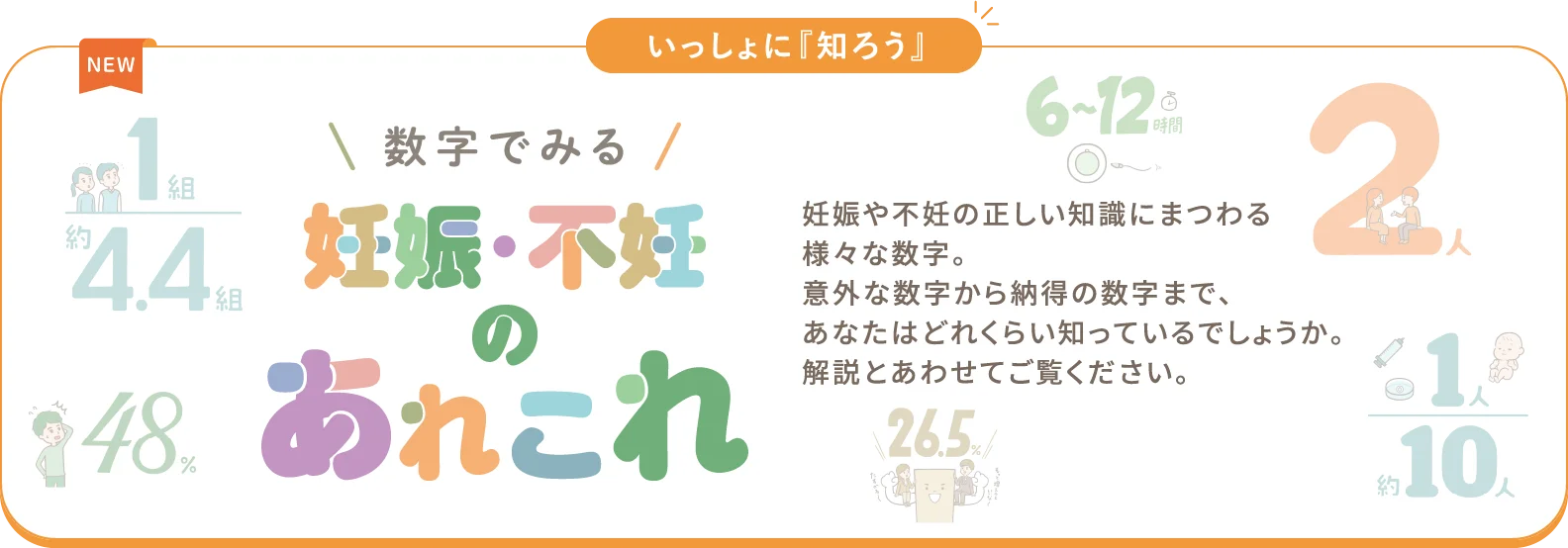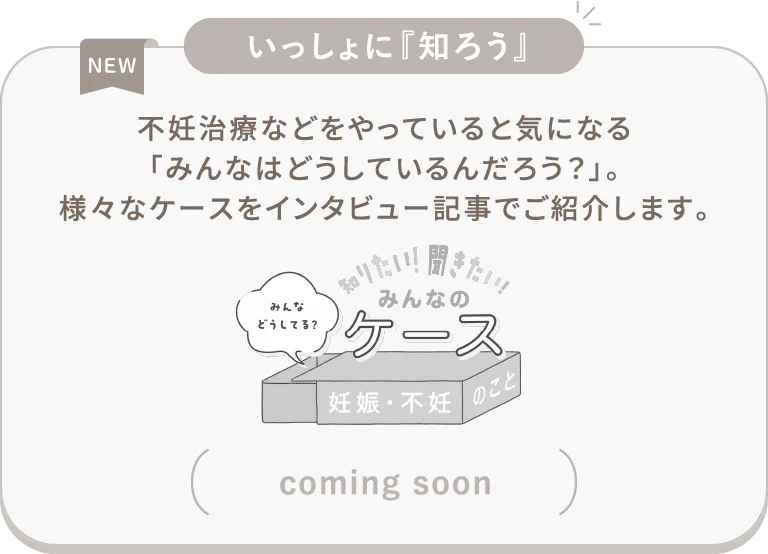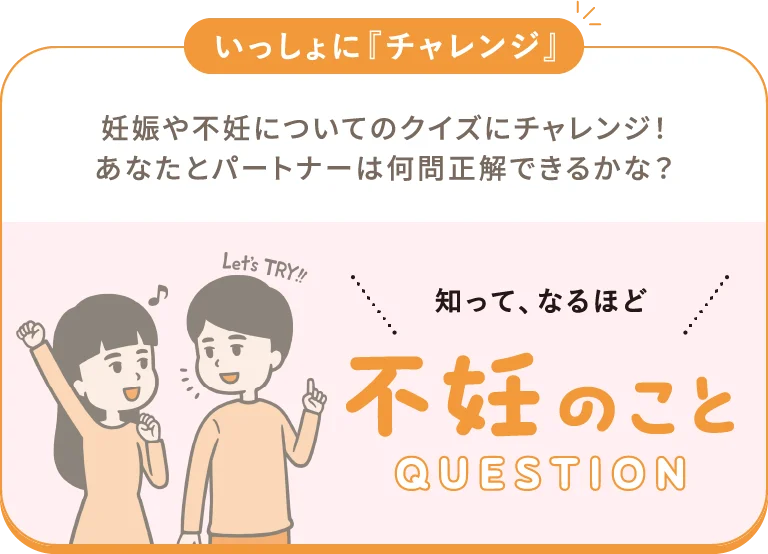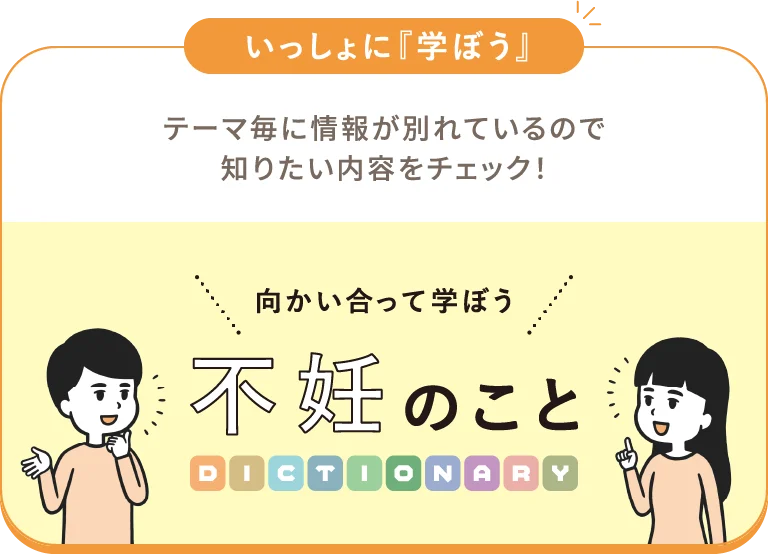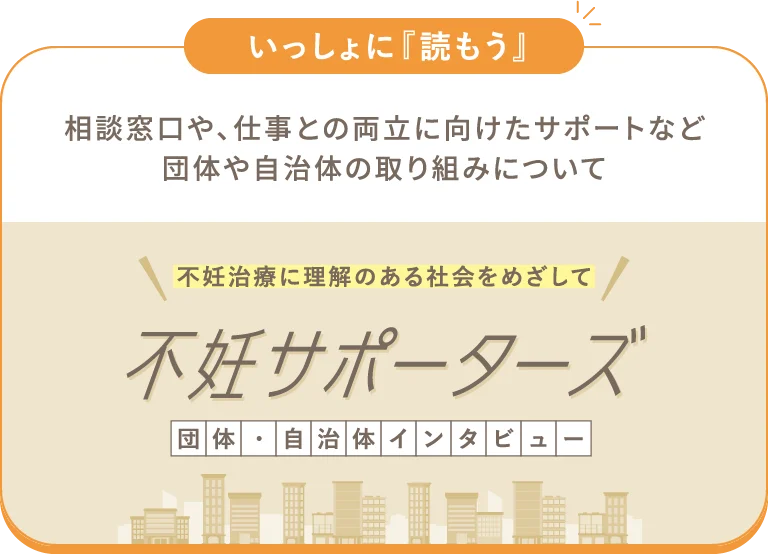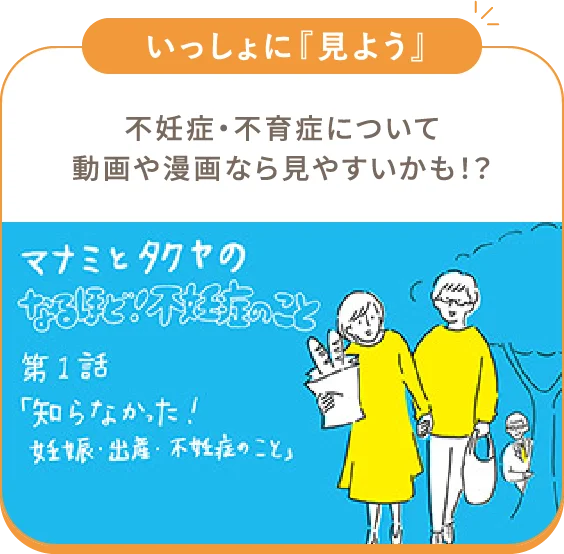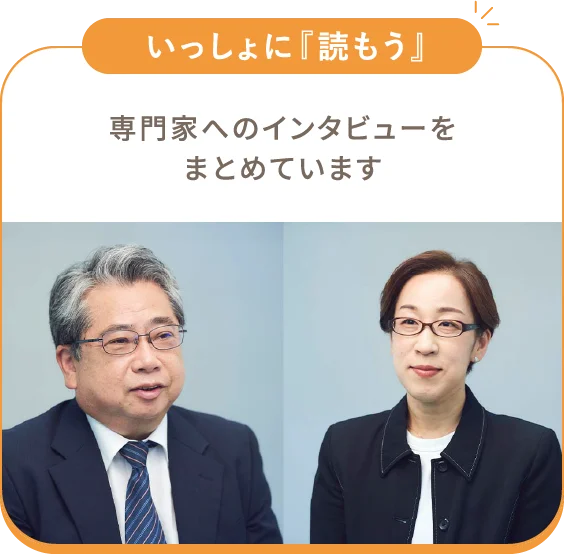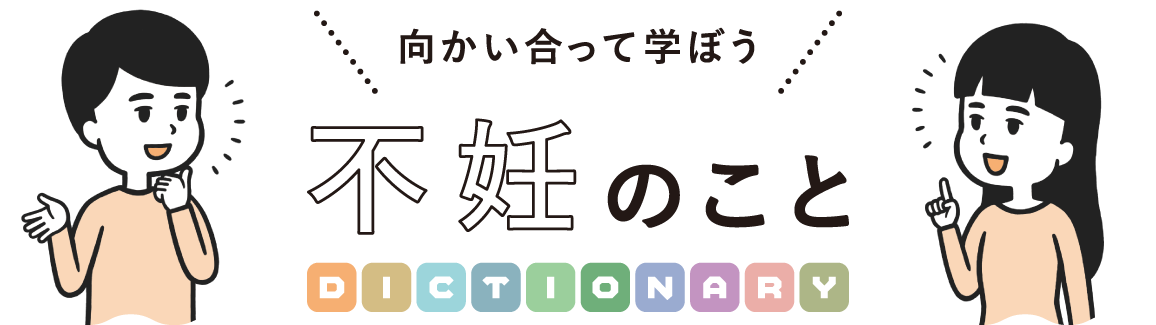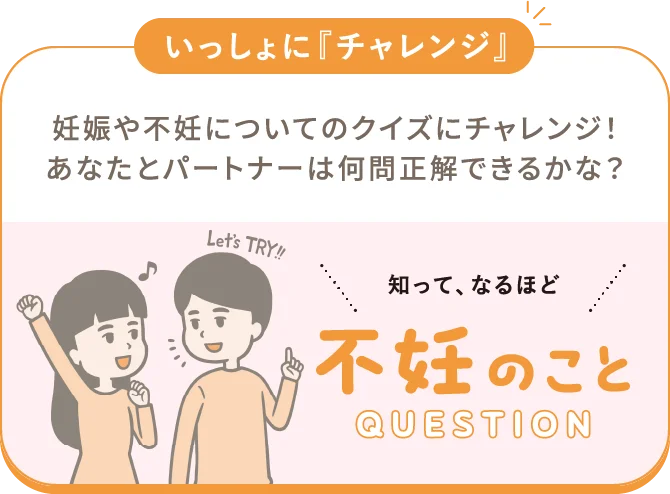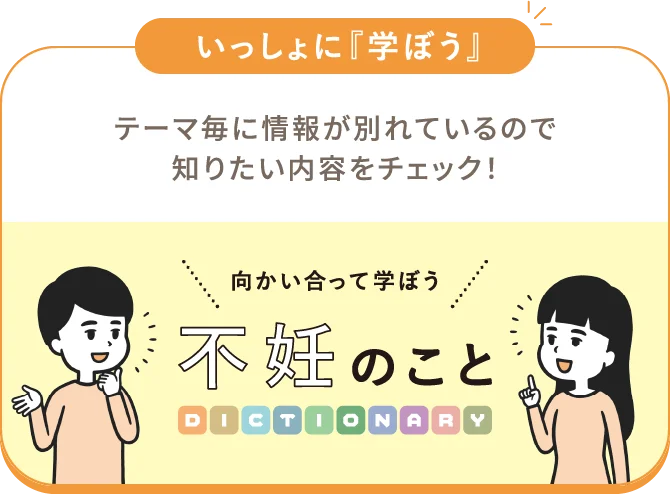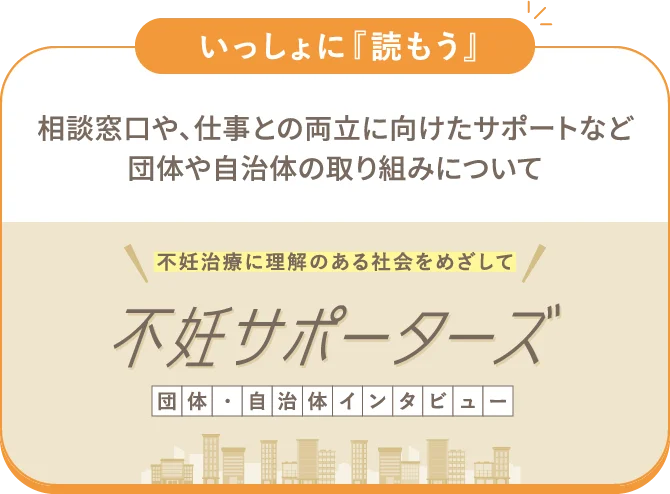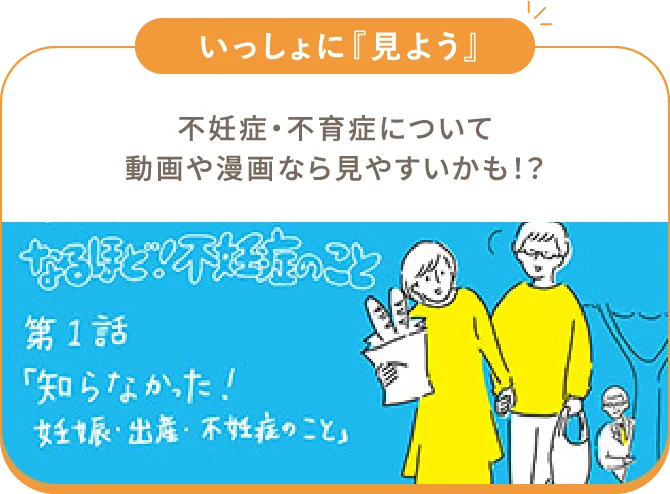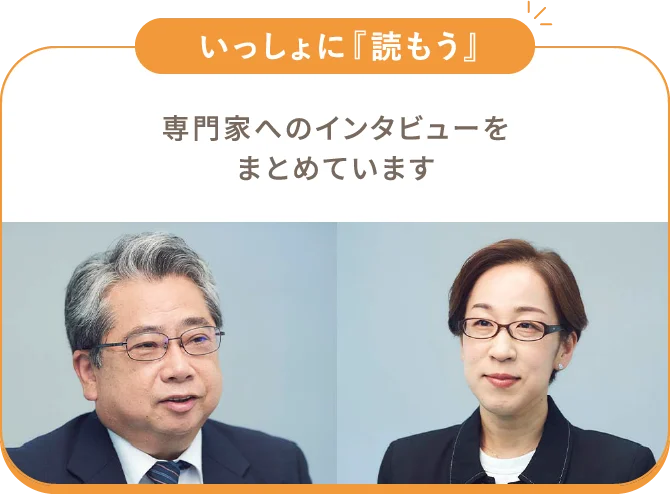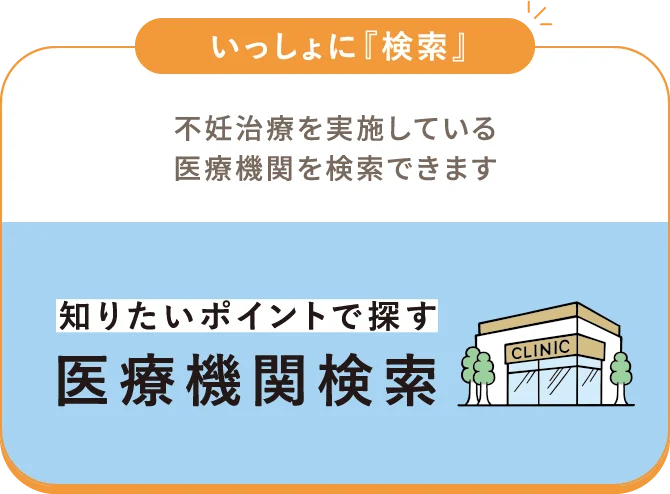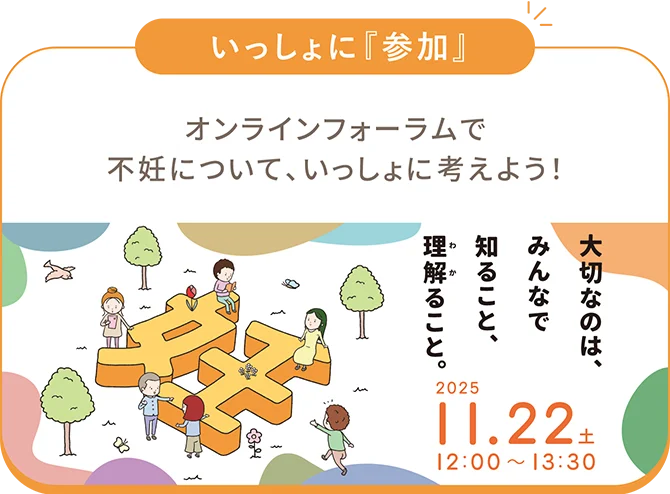不妊症・不育症支援には
「傾聴」が何よりも大切

臨床心理士/公認心理師 桝田智子さん(前列 右)
日本助産師会 専務理事 久保絹子さん(後列 右)・事務局長 髙橋 尚さん(後列 左)
妊娠・出産に関するケアや一生を通した女性のヘルスケアを支援する助産師の団体「日本助産師会」では、こども家庭庁の委託を受けて、不妊症や不育症のサポーターを養成する「不妊症・不育症ピアサポーター等の養成研修」を実施しています。不妊症・不育症当事者の方の癒やしの場にもなっているという研修について詳しく聞きました。
当事者に寄り添う支援が必要
助産師だからこそできるサポートも
日本助産師会が実施している「不妊症・不育症ピアサポーター等の養成研修」。どんな研修なのでしょうか?
布施:この研修は、こども家庭庁からの委託を受けて実施しています。今や、3人に1人が不妊症や不育症に悩んでいるといわれ、その方々に対する精神的なサポートとして医師や助産師、看護師、保健師、心理職などからの専門的な支援が必要であり、同時に同じ経験をした人が寄り添う「ピアサポート」が重要ではないかということで始まった取り組みです。
研修の対象となるのは、医師や助産師、看護師、保健師、心理士など医療専門職の方、そして不妊症・不育症でお悩みの方、不妊治療や流産等の経験がある方、ピアサポートに興味のある方、不妊治療と仕事の両立支援に取り組む方などの一般の方々です。医療専門職と一般の方々のそれぞれに研修プログラムを用意しています。

一般の方々に向けた、不妊症や不育症のピアサポーター養成プログラムの講義では、「男女それぞれの不妊症や不育症の医学的知識と一般的な治療の流れ」「支援に対する制度について」「不妊症や不育症に特有の悩みや不安」「里親や養子縁組制度とその現状・課題」「ピアサポーターとは及び企業での支援について」という5つのテーマについて学びます。
医療従事者対象のプログラムも4つめまでは同じですが、「ピアサポーターとは及び企業での支援」という講義にかえて、流産や死産などを経験した方の心のケアをし、支えていく「グリーフケア」について学びます。講義はグリーフケアとは何か、流産や死産などを経験した方のお話などで構成され、医療現場でそのような方と出会った場合には、心のケアをして立ち直るまで支援をすることが重要だと伝えています。
この研修がスタートしたときはコロナ禍で、研修プログラムはすべてオンラインでしたが、令和5年度からは会場で行う対面研修も実施できるようになりました。対面研修では「自己決定を支える相談技法」というテーマで、講義とグループワークを桝田先生に担当してもらっています。桝田先生は、生殖医療を受ける対象者へのサポートもされていますので、より深く受講者の皆さまに伝わる講義になっているのではないかと思います。
桝田:不妊症や不育症はとても個人的な問題で、そのご夫婦やご家族にとって一生の問題でもあるので、夫婦や家族が自分のものとして受け止め、自己決定することが何より大切です。そのためには何かをしてあげることよりも、まず「傾聴」が必要だということを、講義やロールプレイを通して学んでいただく目的で対面研修を行っています。

グループワークでは、3人1組でそれぞれが相談者、支援者、オブザーバーと役割を交代しながら、ロールプレイと振り返りを行います。いきなり「さぁ、やってください」といっても難しいので、令和5年度はロールプレイに入る前に、イメージしやすいように私が作ったシナリオで布施理事と一緒にデモンストレーションを行いました。受講者から「とてもわかりやすかった」と好評をいただきました。
ロールプレイでは、支援者として「こう言ってあげたかったけれど、うまく言えなかった」という無力感を覚えたり、逆に相談者としては「ただ黙って聞いてくれるだけで安心できた」などの感想が聞かれ、サポートの実際を肌で感じることができるプログラムとなっています。見ているときは簡単そうに思えても、実際にやってみると難しいものですが、その難しさを学んでいただくことがとても大切だと考えています。
朝澤:ロールプレイでは、実際に不妊症や不育症を経験された方が、ご自身の経験を思い出して涙してしまうことも少なくありません。なので、必ず私たち助産師がファシリテーターとして入っています。ロールプレイのグルーピングにも配慮し、研修の間もケアできるチーム体制を組んでいます。例えば、不妊症や不育症を経て、現在は妊娠されている方が受講されることもあり、不妊治療や不育症治療をしている方がつらいと感じる場合もあるためです。受講者の方の心配事を少しでも払拭できればと、意見を出し合って講座をブラッシュアップしています。

日本助産師会が養成講座を行うことの意義は、どんなところに感じていますか?
布施:助産師は不妊症や不育症の方のそばにいる機会が多くあります。専門的な学習をしていて妊娠や出産に関する正しい知識もあり、患者さんに対してどこをケアしていけばいいのかがすぐにわかり、きめ細やかなケアができる。そのような実際に寄り添える立場の人間が、この研修の立案をするのがベストだと思っています。
患者さんや医療従事者の声を
プログラム作成に反映
どんな方の受講が多いですか?
布施:ピアサポーター養成プログラムは、さまざまな方が受講していて、男性も全体の5%ほどいます。ご自身が不妊症や不育症の経験者で、何かできることはないかという思いから参加される方が多く、すでにピアサポーターとして活動している方もいます。
久保:参加者アンケートでは、参加理由として「最新の知識を学びたい」が75%と最多で、そのほかに「今後支援をしていきたい」「ピアサポートに興味・関心がある」「当事者同士で交流したい」「職場で活かしたい」「グリーフケアに興味・関心がある」「ピアサポーターとして活動中なので最新の知見を得たい」などがありました。
医療従事者対象のプログラムの受講者は、助産師が58%と最も多く、看護師15%、保健師13%、鍼灸師4%、培養士・心理士・医師がそれぞれ2%となっています。そのほか、薬剤師や医療事務職、理学療法士などの参加もあります。
男性の参加も増えてきています。参加理由は、「最新の知識を知りたい」がやはり最も多く、そのほか、「今後支援したい」「支援に役立てていきたい」「支援者同士での交流を支えていきたい」などがありました。
参加申し込みは全国からあり、最新の知識をインプットするために複数回受講される方もいます。

各プログラムを作成するうえで、大事にされていることはありますか?
布施:講義の内容は、出産年齢の変化などによる社会のニーズや、専門職であるスタッフの持っている新しい情報などを合わせて、プログラムを実施するチームで話し合って決めています。いちばん大事にしているのは、医療現場で実際に見たり聞いたりする患者さんや医療従事者の声です。
また、不妊治療や不育症治療について以外に、特別養子縁組制度についても必ず入れるようにしています。制度の名前は知っていても、具体的に何歳から迎えられるのか、迎えたい場合はどこに行けばいいのかなどがわからない人も少なくありません。知識として知っておくことで、いろいろな選択肢が広がり、養子を迎える選択肢もあるよということを知ってもらうことができるので、重要だと思っています。
桝田:対面研修で意識しているのは、この問題においての主体はあくまでご相談者なので、「とにかく傾聴することが大切」と伝えることです。
何かをしてあげないと役に立っていないのではないかと思う人も多いのですが、そうではなくて、迷うことも含めてご相談者が決めていくプロセスを邪魔せず、そこに寄り添っていくのがサポーターの役割だということを、いろいろな角度から伝えられるようにと考えています。
特に医療従事者は、積極的にアプローチをしないことに不安を感じる方が多いです。医療従事者の場合は、それぞれの専門性に応じて、例えばご相談者の悩みを医療につなげたほうがいいかどうかなど、何らかの判断をしながら話を聞くということもあると思いますが、やはりあくまでご相談者の自己決定のプロセスを邪魔しないことを大事にしましょう、とお伝えしています。
研修自体が癒やしになっているケースも
布施:ピアサポーター養成プログラムの受講者からは、「誰にも言えなかったけれど、受講者仲間と話すことで同じ思いの人がいることがわかり、自分の中のモヤモヤした気持ちを解消できた」というような感想も多く聞かれます。研修自体が癒やしになっている方も多いので、悩んでいる方の居場所づくりという意味でも、大切に継続していかなければいけないと思っています。
朝澤:令和6年度は対面研修プログラムの新たな企画として、医療従事者の研修後でピアサポーターの研修前となる昼休みに、両者の交流会を1時間ほど設けました。大いに盛り上がり、「初めて培養士さんと話すことができてよかった」などの感想が聞かれましたが、「全員と関わりたかった」「ピアサポーター研修の受講後にも交流したかった」という声も。その点は今後の課題です。
髙橋:また、「男性としてのニーズがあることを知った」「男性としてできることを再認識した」という、男性の受講者の感想や、企業の相談窓口などに所属している方からの「どう支援していったらいいか、具体的な方法がわかった」という声もありました。
オンデマンドの講座については、「新しい知見を得た」「自分の業務や活動に活かせる」という声が多く、満足度が高いというアンケート結果が出ています。

研修を終えたピアサポーターの皆さんはどんな活動をされていますか?
朝澤:ピアサポーターとして地域の中で活動しているケースとしては、まず自治体を通じて活動している方々がいらっしゃいます。
例えば、埼玉県の「プレコンセプションケア相談センター埼玉 ぷれたま」は、埼玉県助産師会が県から委託されて行っている電話相談ですが、この中でピアサポーターが相談に応じています。また、大阪市の「おおさか性と健康の相談センターcaran-coron」でも助産師による電話相談を開設していて、ここでもピアサポーターが活躍しています。
現在立ち上げようとしている、ピアサポーターの養成を促進するためのサイトには、地域でボランティアとして活動しているピアサポートの例を掲載していく予定です。
ピアサポーターの方々からは、「自分たちを必要としている方とつないでほしい」という声も少なくないので、今後の課題ではありますが、そのような機会をつくってどんどん活動していただけたらと考えています。
不妊症・不育症ピアサポーター等
の養成研修