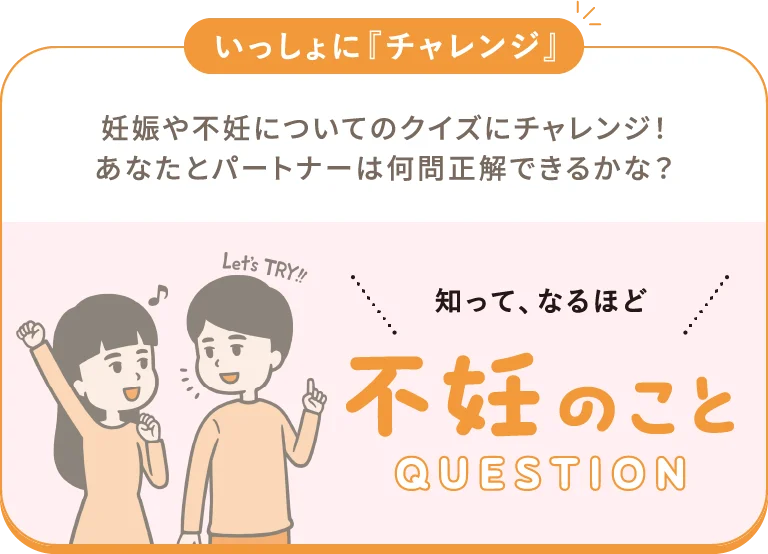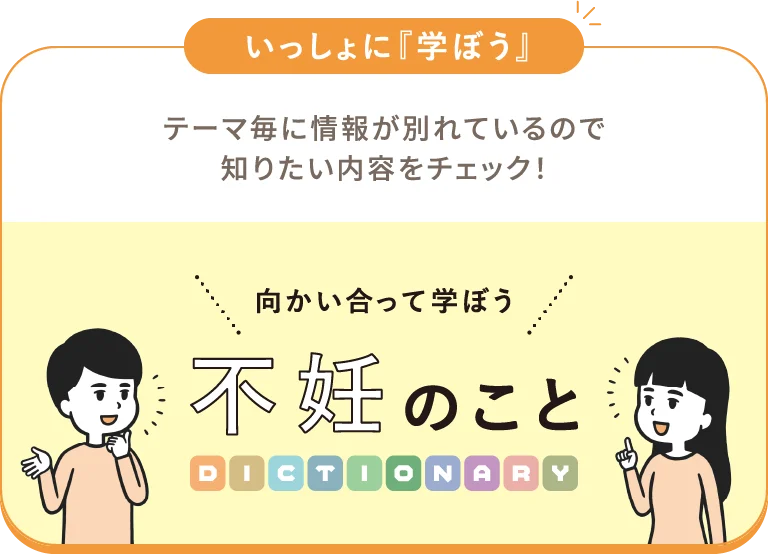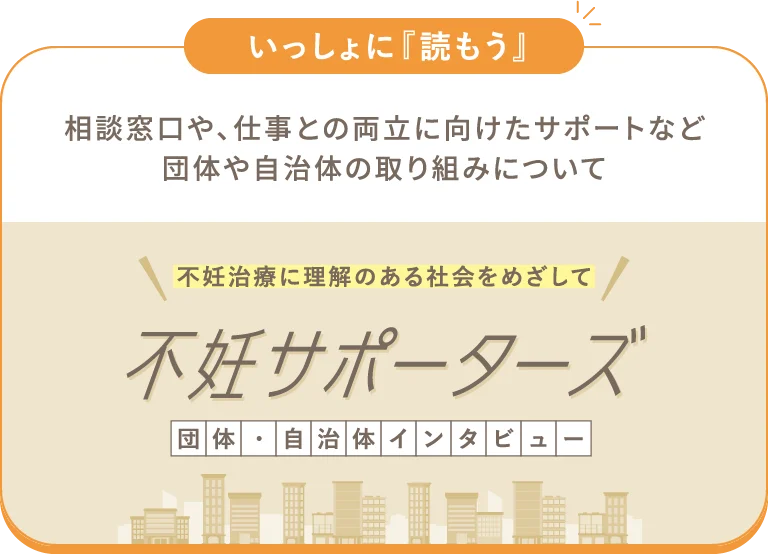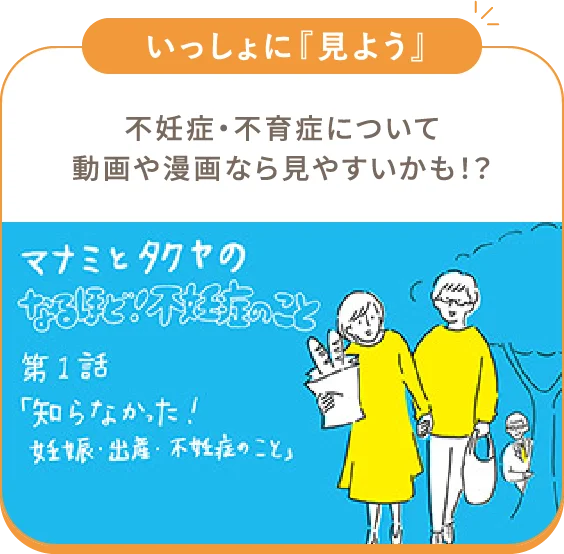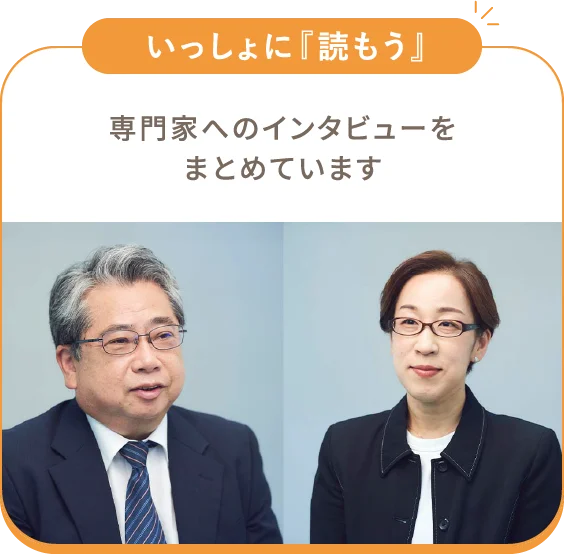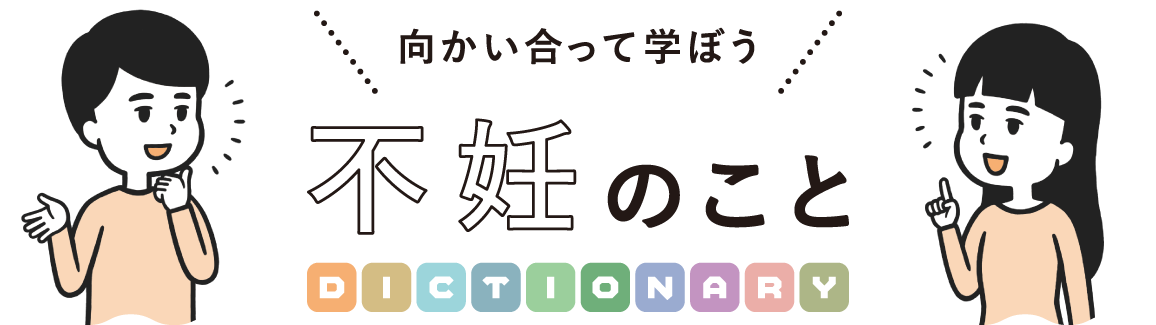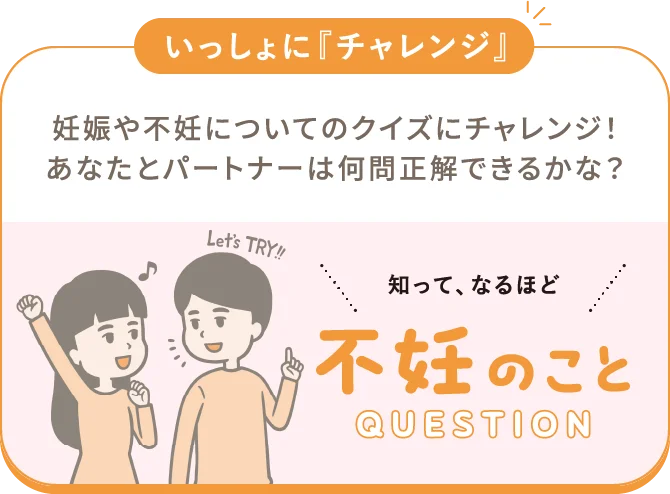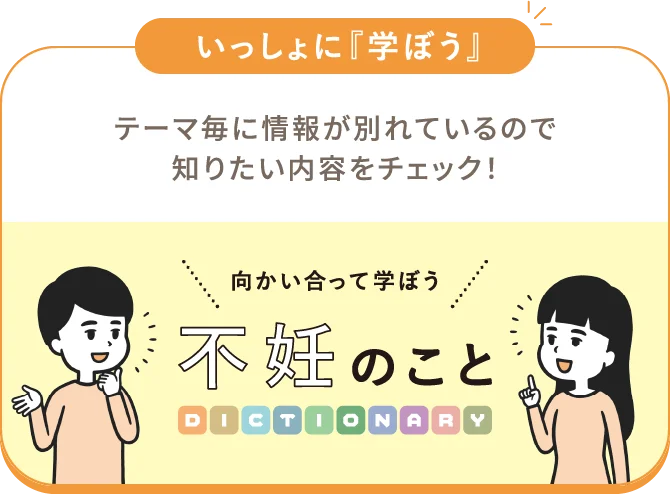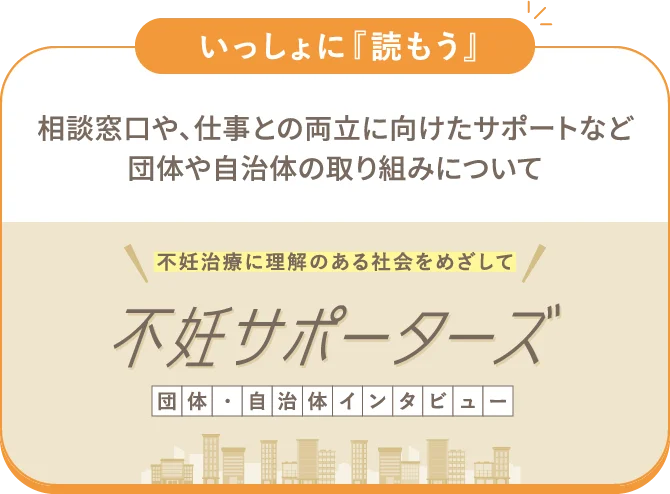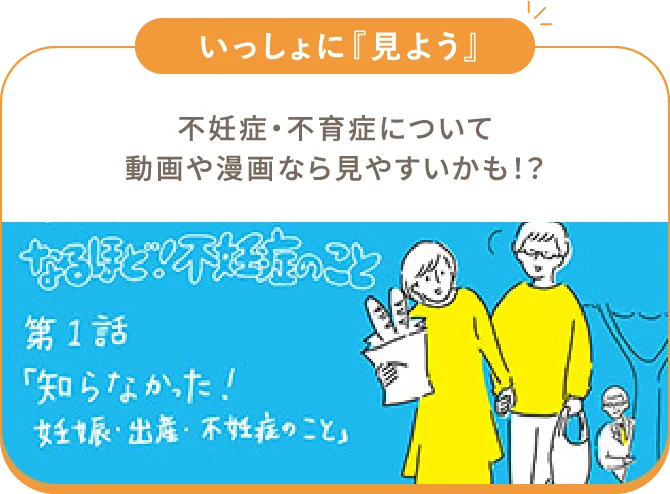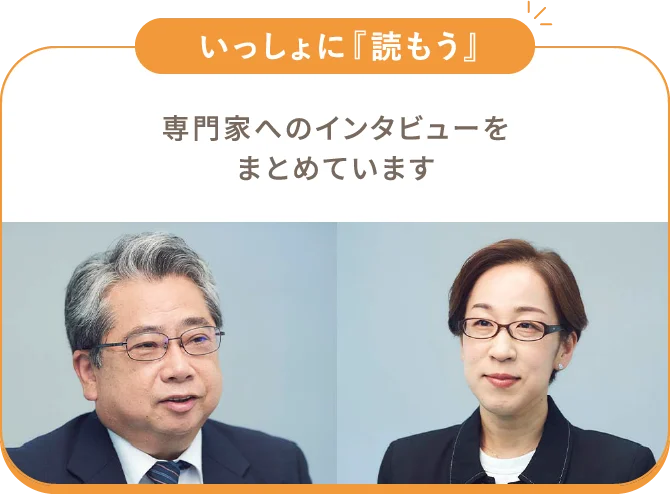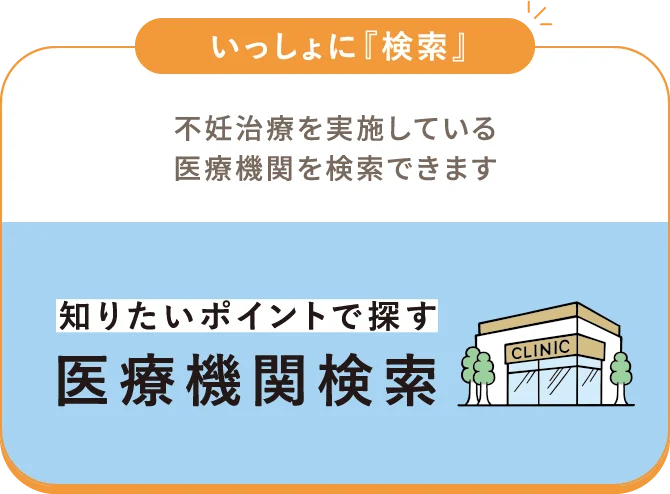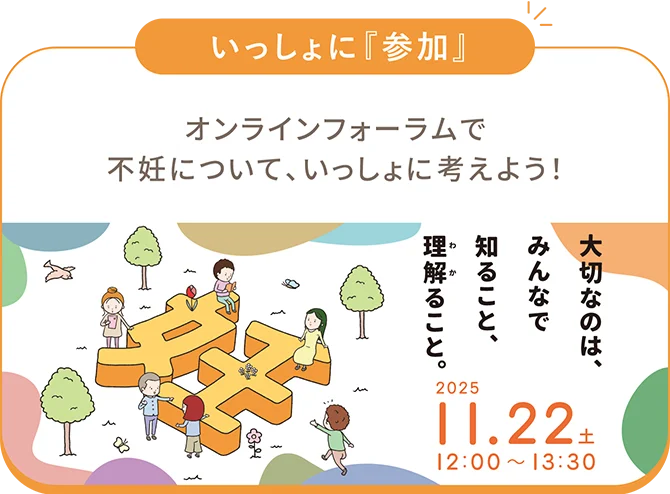私たちをきっかけに、
いろいろな相談窓口があると知ってほしい

不妊症や不育症で治療中の人だけでなく、なかなか授からずに悩む人たちを支援しているNPO法人「Fine(ファイン)」。活動の一環として、不妊症や不育症などにまつわるカウンセリングも行っています。理事長の野曽原誉枝さんに、「Fine」が目指すことやカウンセリングの利用状況、相談内容などについて聞きました。
不妊治療の有無に関わらず、
自分らしい選択ができる社会を目指す
「Fine」とは、どのような団体ですか? どんな思いでスタートし、どのような目的で活動しているのか、お聞かせください。
私たち「Fine」は、治療の有無に関わらず、不妊症や不育症、それらの治療で悩んだことがある人や、なかなか子どもを授からなくてつらい経験をしたことがある人たちが集まってできた自助団体です。
私たちと同じような思いをしないように不妊症や不育症の治療をしている方や悩んでいる方たちの支援をしているほか、治療について社会に正しい情報を広める活動や、患者と医療機関・公的機関の橋渡し、患者の意識と知識の向上などを目的としたカウンセリングや講演会など、さまざまな活動を行っています。
当団体は、不妊治療の当事者が掲示板などで自分の気持ちを発信していたところに同じ経験をした仲間が共感して集まり、2004年に設立されました。その中で、当事者のつらい気持ちをもっと広く知ってもらいたいという思いが強くなり、社会に広めやすくなるように2005年1月18日にNPO法人格を取得しました。

設立当初は、「不妊治療」という言葉も広まっておらず、子どもを授からなくて悩んでいることを周りに話せる雰囲気もなくて、社会的にはマイノリティでした。それから10年たって私がメンバーに加わったときには、独自の助成金制度を設ける企業が現れるなど、少しずつ不妊治療や不育症治療への取り組みが見え始めてきました。
ですが、当事者の相談を受けてサポートをしても、普段暮らしている地域やコミュニティでまたつらい思いをし、相談に戻ってくる人も少なくない状況でした。
2024年に迎えた設立20周年には、不妊治療を受けて生まれる子どもも増え、社会にも不妊や不妊治療という言葉が浸透して、かなり変わってきたと実感しています。
また、不妊治療が保険適用になったとき、積極的に子どもを望まない人にプレッシャーがかかっているという話もあり、「子どもがいることだけがハッピー」ということにはならないようにしなければと、改めて認識しました。それもふまえ、不妊治療を受けることはもちろん、受けないと決めることや夫婦ふたりで生きていくこと、里子を迎えることなど、不妊にまつわるすべてについて、自分らしい選択ができる環境や社会をつくりたいと考え、活動しています。
多く寄せられる悩みは
「なかなか妊娠に至らない」
「年齢のことが不安」
Fineの「不妊ピア・カウンセリング」とは、どのようなものでしょうか?
Fineの「不妊ピア・カウンセリング」では、不妊で悩んだ経験がある人が、カウンセリングのスキルや知識を身につけたうえで相談に応じています。カウンセリングはオンラインでの面接45分と通話による40分の2種類があり、通話は無料です。顔を出さずに相談できる通話のほうが多いですね。
寄せられる悩みで特に多いのは、「なかなか妊娠に至らなくてつらい」「40歳を超えてしまった」という2つです。40歳以上では、体外受精や顕微授精の保険適用の回数が3回になってしまうため、あせる方が増えてきます。治療の回数については、若い方でも保険適用の治療の回数が6回、5回、4回とカウントダウンされていくことで「どうしよう……」とあせっている方も少なくありません。
「不妊治療のやめどきがわからない」「夫に問題があるのに自分ばかり頑張っている」という声もあります。不妊治療はお金も時間もかかり、身体的な負担も大きいので、なかなか決断が難しいですし、薬や注射などの治療を受けるのが主に女性だけという面で不公平感を覚えてしまうケースも。一方で、20代~30代前半ぐらいの方からは、「これから不妊治療をしようか迷っている」という悩みも聞かれます。
男性からもご相談があります。男性不妊の悩みもありますが、「不妊治療がうまくいかず、妻がとても落ち込んでいるけれども、どう声をかけていいかわからない」というご相談もありました。
ご相談にはどのようなカウンセリングをしているのですか?
カウンセリングでは、ご相談者が自分の気持ちに気づくためのサポートをします。カウンセリングを始めるときは、ご相談者は自分の気持ちに向き合えていなくて、「つらい」としか言葉にできないことが多いので、何が原因で今の状態になっているのか、その奥にある、その方が望んでいることは何かを一緒に探っていきます。
例えば、「41歳になってしまった」というお悩みであれば、どんなところにいちばんつらさを感じるか、どんな不妊治療を行っているか、パートナーとの関係はどうか、などいろいろな話を伺い、話をまとめたり伝え返したりしながら、ご相談者が抱えている感情を共有し、丁寧に紐解いていきます。
そこで「パートナーとうまくコミュニケーションが取れていない」という答えが返ってきた場合、さらに問いかけて「不妊治療を続けていくうちにパートナーと感じ方が違ってきてしまった」という話が出てきたなら、それはお金の問題なのか、パートナーからの声かけが少ないことなのかなど、いろいろな角度から尋ねます。

そうして、ご本人が気づいていない気持ちや本音について、これからどうしたいか、どんな思いを持っているかを問いかけていきます。「これがいいと思う」「こうしてください」などのアドバイスをするのではなく、ご相談者が自分で選択肢を設定し、そこから自分で選ぶことが大切だと考えています。
「友だちと集まったとき、子どもの話題になってつらかった」という場合なら、その集まりに絶対に行きたかったかどうかを尋ねたり、「行かないという選択肢もありますか?」と問いかけたりします。やはり、自分で自分を守る策も必要です。断り方についても、どういう伝え方をしたらいいのか一緒に考え、ときには不妊ピア・カウンセラー自身の経験をお伝えすることもあります。
不妊治療経験者から
不妊ピア・カウンセラーへの道もサポート
カウンセラーの育成も行っているそうですが、養成講座についてお教えください。
いくつかコースがありますが、「ライセンス取得1年短期集中コース」では、自宅で自分のペースで学習を進められるe-ラーニングと、ロールプレイなど実習を行う3回のスクーリングで学びます。
内容は、公認心理師や臨床心理士などの先生が講師をつとめる心理学の講座が多く、その他、生殖医療分野の医師がスタンダードな治療のほか、先進医療、卵子凍結、不育症治療などの最新の医療情報、グリーフケアなどについて講義する講座などがあります。コースを修了し、認定試験に合格すると、Fine認定の「不妊ピア・カウンセラー認定証」が授与されます。
ただ、これらの講座では、受講者が自分のことを振り返る必要があります。「なぜ、あなたはこんなにつらいと思ったのか」を掘り起こさなければなりません。そのため、残念ながら途中でやめてしまう人もいます。カウンセラーとして相談を受けるようになると、相手の話で自分の記憶がよみがえってくることもあります。カウンセラーにはある程度の強さが必要です。